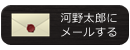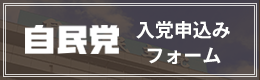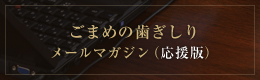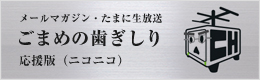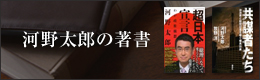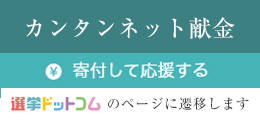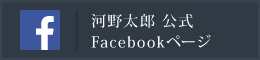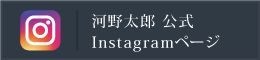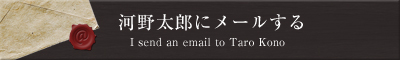- HOME
- » ごまめの歯ぎしり » 50 2024年10月から(石破政権) » 社会保障改革2025 年金問題を解説する-2 国民年金の問題
社会保障改革2025 年金問題を解説する-2 国民年金の問題
2025.03.03
現在の国民年金にはいくつもの問題があります。
現在の国民年金は、第一号被保険者は収入の多寡にかかわらず、月
所得が少ないほど所得に対する年金保険料の負担率が高くなる、す
他方、第三号被保険者は保険料負担なしで満額の基礎年金を受給す
基礎年金を受け取るためには、受給に対応する保険料を負担する必
年金保険料を480ヶ月納めて、満額68,000円の基礎年金を
保険料を免除されても、基礎年金の半分は国庫負担であるため、4
しかし、保険料を免除ではなく未納にしてしまうと、年金の半分も
現役時代に所得が少なく、保険料を免除や未納にしてしまう人もいるため基礎年金の受給額は平均すると六万円にも満たないのが現実です。
満額の基礎年金68,000円でも老後の生活を維持するのは困難ですが、それよりも実際の年金額が少ないと年金生活は厳しくなります。
480ヶ月の保険料を支払って受け取る基礎年金額が68,000円に対して、年金保険料を負担せず、基礎年金を受け取ることができないと生活保護に頼ることになります。
しかし、その生活保護の生活扶助費が満額の基礎年金額を上回る現実があると、年金保険料を支払わず、万が一の時は生活保護でよいと考える人が増えていかないでしょうか。
最新の2023年度のデータ(2024年度は2025年3月末まで)によれば、第一号被保険者の中で保険料を満額納付している人の割合は五割以下です。
国民年金の保険料の納付率は、保険料を免除される人が増えると分母が小さくなるため、分子となる納付者の数が同じでも納付率は上がっていきます。
しかし、実際には保険料を満額納付しない人が増えれば、将来の低年金者、無年金者が増えていきます。
保険料負担に応じて年金を給付する制度では、未納や免除が必ず出るため、年金が減額される人が出ることを避けることができません。
仮に現在の基礎年金額が老後の世活を支えるために最低限必要な金額だとしても、年金額がそれに満たなくなってしまう人が出ることを避けられません。
そのため、保険料方式の年金では、老後の最低生活を保障することはできません。
年金保険料を免除や猶予しても、それに対応する分、年金が減額されるため、年金財政には大きな影響は出ないかもしれませんが、無年金者、低年金者は生活保護など、財政で支えていくことになります。
そのため、免除や未納がでると財政そのものに大きな影響が出ることになります。
すべての老後に必要な最低保障をするためには、保険料ではなく税
年金だけで老後の生活全てを支えようとするものではないといっても、現実には多くの高齢者世帯にとって、年金が唯一の老後の頼りです。
保険料方式の年金制度で支えきれないところを税財源の制度で支えなくてはなりません。
それを生活保護でやるのか、税財源の年金制度でやるのかということです。
保険料方式の年金では支えきれない高齢者世帯を、たとえば負担と給付の関係がわかりやすい消費税
16,980円の年金保険料負担が無くなるので、消費が少ない世
一定以上の年金や年金以外の収入があったり、資産がある人には最低保障年金を逓減するあるいは支給を停止することにすれば、消費税率は下げられます。
生活保護などのセーフティネットと統合することにより、財政的な無駄も削減することができます。
これまでの年金制度の微修正ではなく、抜本的な年金改革の議論が必要です。